
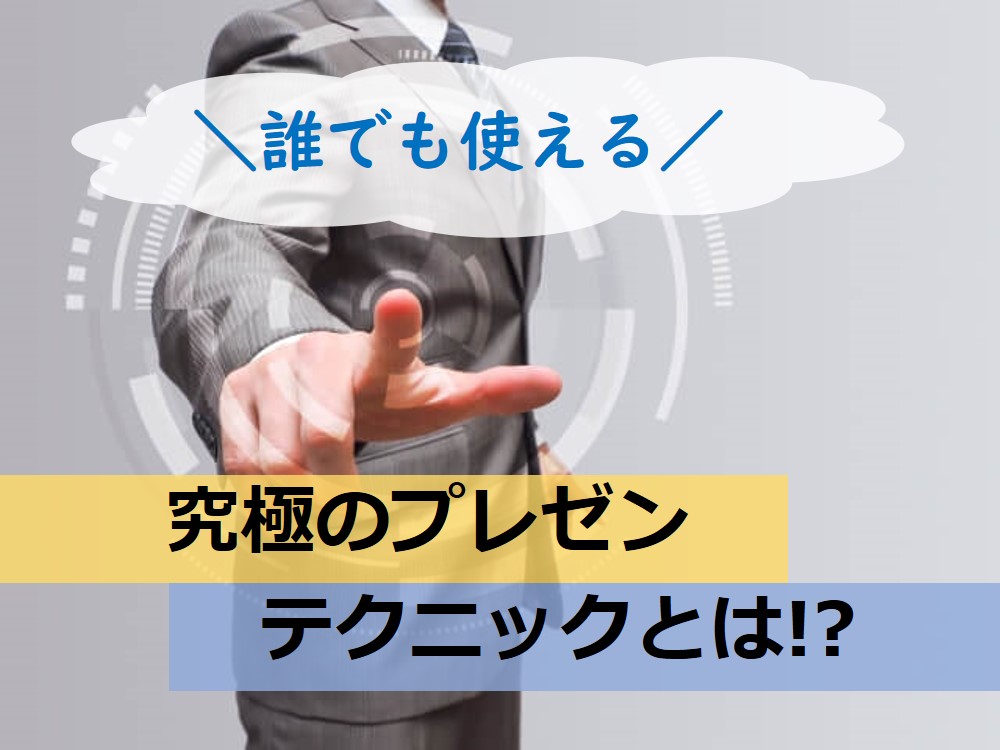
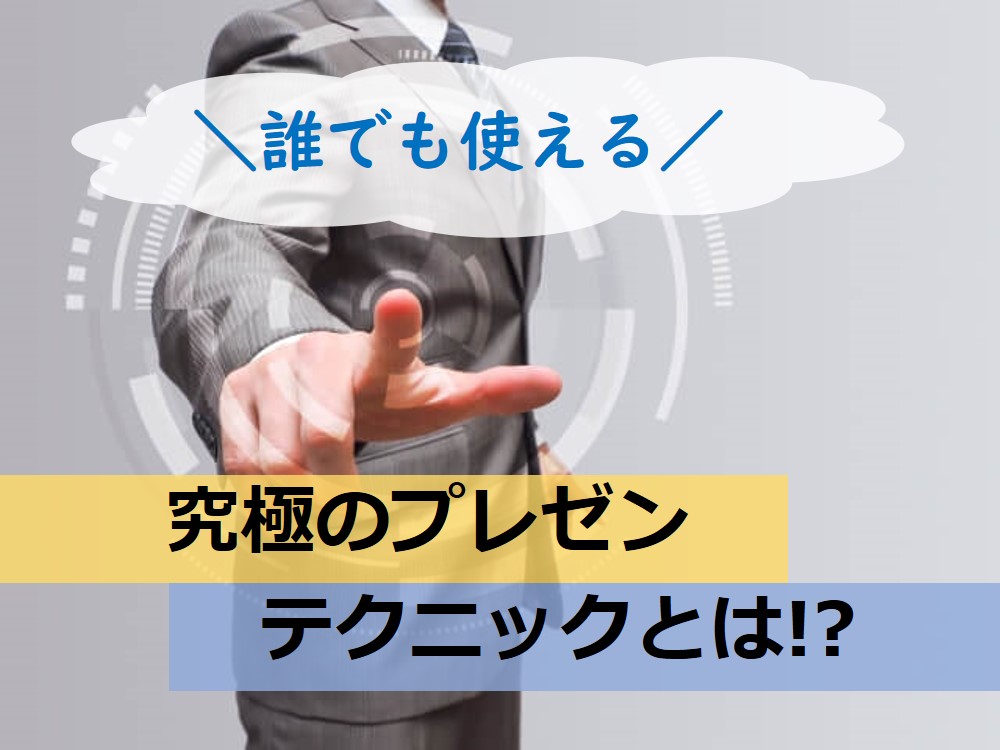

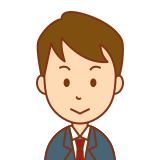
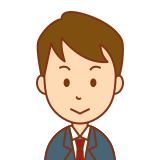
「リーダーに必要なスキルとして、プレゼン力を磨きたい!具体的にどうすればいいの?」

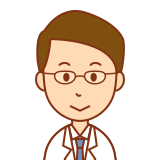
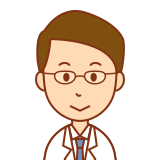
「プレゼン力を磨いて一目置かれる人になりたい!」
このように、過去も未来もプレゼン力はビジネスパーソンにとって非常に重要なスキルです。
また、奥さんに旅行を提案したり、夫に家事掃除を手伝ってもらったり、子供に勉強してもらうためにも、プレゼンは必要になってきます。
プレゼン力を磨いておけば、ビジネスシーン以外にも幅広く活用できます。
しかし、
「プレゼンのテクニックを習得するのは難しそう。」
と考える人は多いでしょう。
たしかに、プレゼンのテクニックは多岐にわたります。
しかし、本当に重要なテクニックさえ習得してしまえば、すぐにプレゼン力は向上します。
そのテクニックは、本記事に超具体的にまとめています。



プレゼン力を向上させて素晴らしい生活を手に入れましょう!ワクワクしながら読んでくださいね!
誰でもすぐ使える究極のプレゼンテクニックとは?
さあ、さっそく究極のプレゼンテクニックについて解説していきます。
私は、社内でプレゼンの天才と称されたこともあります。
そのテクニックを余すところなく超具体的にまとめています。



期待して、読み進んでもらえればと思います。
緊張を和らげる10のテクニックを駆使する
「プレゼンってなると、どうしても緊張しちゃうんだよね・・・。」
そもそも人前で話すことが苦手な人は、どれだけ練習を積んでもガチガチに緊張してしまい、プレゼンが上手くいかないと悩んでいる人が多いです。
そのため、まずは緊張を和らげるテクニックを知り尽くしましょう。
誤解して欲しくないのが、プレゼンで全く緊張しない人はほとんどいないということです。
プレゼンの緊張はあくまで和らげるもので、完全になくすことはほぼ不可能とお考え下さい。
ちなみに、緊張は悪いことではありません。
少し緊張した方が、むしろ成果は上がることが分かっています。
悪いのは、過度に緊張してしまうこと。
プレゼンの時にガチガチに緊張してしまう人は、下記の10のテクニックを駆使してみて下さい。
①手の置き場を作るだけで精神が安定する
②キャラクターになり切って話す
③プレゼン資料を見ずともスラスラ言葉が出てくるまで練習する
④人前で話す30分以上前に食事は済ませる
⑤時間に余裕をもって本番に備える
⑥直前にプレゼン内容は変更しない
⑦深呼吸を繰り返す
⑧直前に軽く水を飲み、ノドを潤しておく
⑨足裏に意識を向け、地面に根を張るように立つ
⑩聞き手をカボチャと思う
「もっと詳しく知りたいよ!」
という方へ。
詳細については、下記の記事でまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
【人前で緊張しない方法】プレゼンの達人が教えるあがり症克服10の技



緊張をコントロール術を学んでおけば、プレゼンは怖くない!むしろ自分の力を示す最高の場面になります!
PREP法でプレゼンする
PREP法でプレゼンすると、聞き手が理解しやすいので、おすすめです!
P(Point:結論)
R(Reason:理由)
E(Example:事例)
P(Point:結論)
の略称です。
PREP法は、プレゼンで非常に重宝するテクニックです。
結論を先に伝え、補足説明を付け加え、最後にもう一度結論を伝えるというスタイルです。
結論が分かりやすい!
筋道立てたストーリーなので理解しやすい!
もう一度結論を言うことで、聞き手のインパクトに残る!
このように、PREP法はスピーディーに結論を伝えられるので、早急に結論を知りたがる現代社会のニーズに合っています。
PREP法と対になる話し方として、結論を引っ張って最後に伝えるストーリー型もあります。
しかしストーリー型はなかなか結論が出てこないので、途中で飽きられる可能性があります。
なので、迷ったらPREP法でプレゼンを作れば間違いないです。
それほど万能なんです。
PREP法の伝え方の一例を挙げます。
P:楽に痩せたいなら、ドクターエアの振動マシンが最もおすすめです。
R:なぜなら、筋肉は伸び縮みすることで鍛えられますが、振動によって効率的に筋肉を伸び縮みさせられるからです。さらに、ただ乗るだけでテレビを観ながらできるので、誰でも継続しやすいこともおすすめの理由です。
E:実は私も半年間ほど使っていますが、もうすでに8キロも痩せています。
P:従って、楽に痩せるなら、ドクターエアの振動マシンの選択がベストだと判断します。
この通り、しっかりと筋道を立てて話せば、どんな難解な内容でも、しっかりと相手に伝えることが出来ます。



PREP法、最強!
専門用語・横文字は極力減らす
「ついに私たちはカスタマーとコンセンサスに至り・・・」
「RFQの依頼を受けましたが、デビエーションリストが無く・・・」
⇧のように、専門用語や横文字は、聞き手の理解度を著しく下げます。
同じ分野の専門家同士が集まる場ならば、専門用語を多用しても問題ないことが多いです。
しかし、部署内での小さなプレゼン以外ではそんな場は滅多にありません。
かならずその分野に精通していない人がいますので、その聞き手たちは理解できないでしょう。
プレゼンは話し手のためにあるのではなく、聞き手のためにあるもの。
この意識は常に持ち、誰にでも簡単に分かりやすい言葉で伝えることが良いプレゼンターになります。
専門用語や横文字を使うほどデキるプレゼンターという誤解をしている人が多いので、気を付けましょう。



極論を言えば、中高生にも分かるレベルまで簡単な言葉で喋れたら理想ですね。
念仏のように「プレゼンは聞き手ファースト」とつぶやく
これ、私が未だに実践し続けていることです。
プレゼンの直前になると、
プレゼンは聞き手ファースト!
プレゼンは聞き手ファースト!!
プレゼンは聞き手ファースト!!!
と何度も何度も心の中でつぶやきます。
頭の中では聞き手ファーストが大切だと意識していても、プレゼンの緊張で頭から抜け落ちてしまうことがしばしばあります。
プレゼンが終わってから
「ああ、今回も自分が喋ることに夢中で聞き手に意識を向けられなかった・・・。」
と何度も何度も後悔したものです。
しかし、プレゼンは聞き手ファーストと本番直前につぶやくようになってからは、聞き手をないがしろにすることは無くなりました。
効果は絶大ですね。
プレゼン直前に聞き手を強く意識でき、さらに副次的な効果としてルーチンワークになって心が落ち着きますので、ぜひお試しください。



もう一度言いますが、「プレゼンは聞き手ファースト」です。お忘れなく!
プレゼンは出だしが肝心!初頭効果で立証済み
多くの人のプレゼンを見ていると、とにかく真ん中の結論や根拠にばかり力を入れており、最初を軽んじている人が多いように思います。
タイトル言って、
背景目的をちゃんと説明して、
さあいよいよ中身の話ですよ!
こんなプレゼンが多すぎます。
心理学の世界では、初頭効果といって、人間は最初の出来事を強く記憶に残しやすい傾向にあることが分かっています。
つまり、聞き手がプレゼンを聞き終わった後、さらっと流したタイトルや背景目的のところの印象が強く残っています。
「あのプレゼンター、淡々と喋っていたなあ」
という最初の印象が強く残ってしまいます。
そして次のプレゼンを聞いているうちに、あなたのプレゼンのことなど忘れてしまいます。
よって、初頭効果で
「このプレゼンは他のプレゼンとは明らかに違うぞ!」
と聞き手に思ってもらうことが大切です。
プレゼンの最初のインパクトを上げるテクニックを下記の通り紹介します。
・第一声を甲高く大きな声にする
・一枚目の表紙のデザインを目立たせる
・一枚目のスライドでアニメーションをいきなり入れる
・プレゼンターの実体験から入る(一流はよく使うテクニック)
・いきなり身体の動きを入れて聞き手の資格情報にインパクトを与える



どれもこれも簡単にできるのにインパクトに残りやすいテクニックです。
費用対効果が大きいので、ぜひおすすめします。
アイコンタクトは全員と取る
プレゼン資料やパソコンばかりを見てプレゼンする人が多いですが、これは当然NG。
アイコンタクトは全員と取って下さい。
メラビアンの法則というものがありますので、簡単に解説します。
人は、
・視覚情報から55%
・聴覚情報から38%
・言語情報から7%
情報を取得すると言われています。
これがメラビアンの法則です。
つまり、あなたの言語情報はたったの7%しか影響を与えません。
あなたの顔を聞き手に見せた方が、聞き手は視覚情報をフルに活用できるようになります。
目は口程に物を言う
という言葉もあるぐらいですからね。
またよくある過ちが、
反応の良い聞き手にばかり話しかけてしまう
役職の高い人にばかり語りかけてしまう
ということですが、私個人的には聞き手には等しく接しないといけないと思います。
※意思決定者に向けてプレゼンするべきという人もいますし、目的に応じて、どちらも正解になりえます。
聞き手が多い場合は、一人数秒でも構いませんので、とにかく多くの方の顔を見ること。
これがプレゼン中に実践できるようになると、あなたのプレゼン力は相当高くなっていると自信をもって言っていいでしょう。



プレゼン中にアイコンタクトまで気を回せるようになったら、あなたは立派なプレゼンターです!
アドリブを極力控える
「え、一流のプレゼンターってアドリブが上手いんじゃないの?」
と意外に思う人は多いかもしれません。
しかし、至高のプレゼンは積み重ねた練習の上に成り立つものなので、アドリブを入れていてはプレゼンの質が下がってしまいます。
一流のプレゼンターがアドリブを入れているように見えるのは、色んなパターンを想定しているからです。

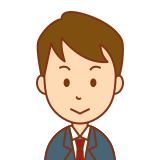
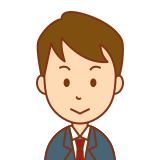
「聞き手の反応が少なかったらこの言葉を使おう。」
「聞き手が少なかったら聞き手に歩み寄ってより身近にプレゼンしてみよう。」
このように、限られたパターンの中から選択しているだけなのです。
アドリブと言えばアドリブですが、完全なアドリブなどは入れません。
このテクニックは場数を踏んだ経験から得られたものなので、あなたがいますぐ取り入れるのは難しい可能性があります。
基本的に、アドリブを入れてデキるプレゼンターを演出しないことですね。



本番になると冷静さを欠いてしまい、練習では全く言わなかったアドリブを入れてしまう方は要注意です。(かつての私です。)
プレゼンテクニックまとめ
それでは、本記事でご紹介したプレゼンテクニックを下記の通りまとめます。
②PREP法でプレゼンする
③専門用語・横文字は極力減らす
④念仏のように「プレゼンは聞き手ファースト」とつぶやく
⑤プレゼンは出だしが肝心!初頭効果で立証済み
⑥アイコンタクトは全員と取る
⑦アドリブを極力控える
この7つのルールを徹底できれば、まず間違いなくあなたのプレゼン力は向上します。



あなたのプレゼン力が劇的に向上することを願っております!
※本記事をブックマークし、ぜひ定期的に振り返って下さい。何度も読み返し実践することで、必ずあなたのプレゼン力向上の手助けになれると確信しています。ブックマークをおすすめします。
※本記事が少しでもあなたのお役に立てたなら、下記のシェアボタンで、ぜひ本記事をみんなにもシェアしてあげてください。
【プレゼンの極意①準備編】誰もが唸るプレゼンが上手くなるコツや方法
【プレゼンの極意②資料編】誰もが唸るプレゼンが上手くなるコツや方法
【プレゼンの極意③練習編】誰もが唸るプレゼンが上手くなるコツや方法
【プレゼンの極意④本番発表編】誰もが唸るプレゼンが上手くなるコツや方法



⇧これ全て読んで実践で練習を積めば、絶対にあなたのプレゼン力が劇的に向上することをお約束します。
ー以上ー

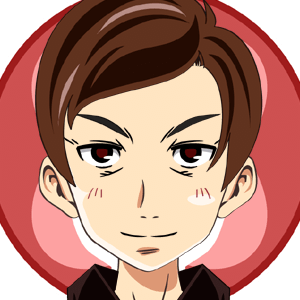
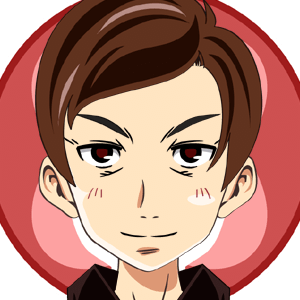
「あなたのビジネス力の向上、全力で支援します!」をモットーにした、自動車業界の大手メーカーの会社員です。
超人的な成功者のリーダー論ではなく、普通の職場・現場に近くて実用的なリーダーシップ・ビジネススキルの持論を展開します。
激変の時代でも活躍できるよう、あなたをブログで全力支援します。
私のプロフィール詳細はこちら!まずは私を知って下さい!
Twitter:@katsuhiroleader ←有益情報を届けますので【フォロー】頂けると嬉しいです。
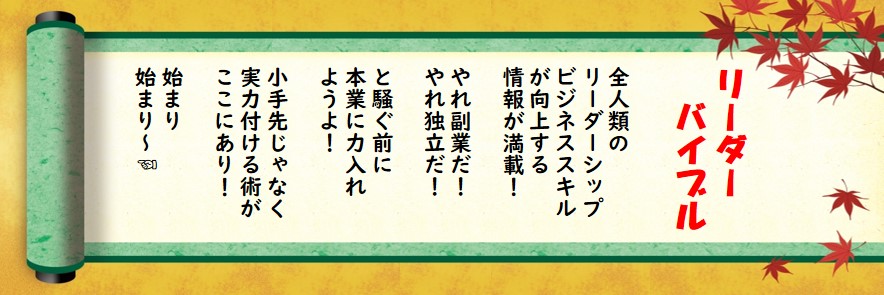

コメント